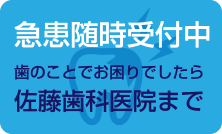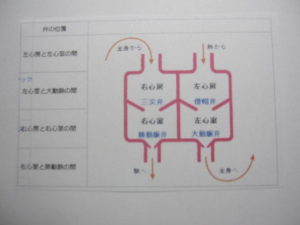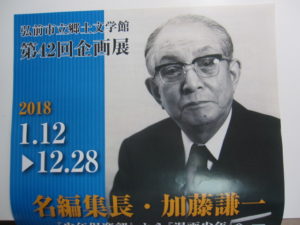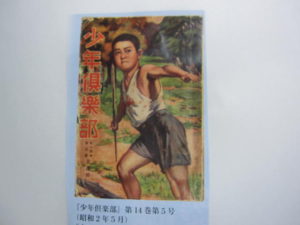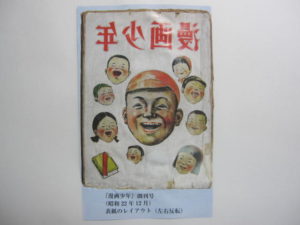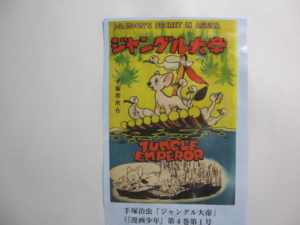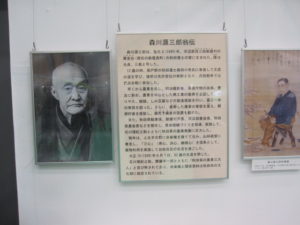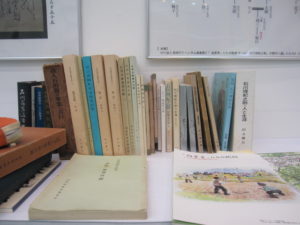2019年3月2日
統計上は「口腔がん」と「咽頭がん」はまとめて登録されますが、近年口腔・咽頭がんの死亡率は増加しています。男性、女性ともに罹患患者が増え、死亡率が高くなっています。今後も増加が予想されます。
口腔がんは高齢者に多くみられるがんですが、高齢化社会を迎えて要介護者や認知症患者の口腔に多くみらられることになります。早期発見、早期治療が大事になります。
憂慮すべきことがあります。それは近年世界中で若者の口腔がん患者が増加していることです。タバコを吸わない、飲酒もしない若者に口腔がんが明らかに増えていることが、イギリスやアメリカではっきりしてきたのです。日本も同様です。

左から 舌ブラシ デンタルフロス 洗口液 歯間ブラシ
口腔がんの早期発見のために健診制度を充実したり、歯科医療者の健診技術の向上をはかる取組が始まっています。
口腔がんの予防で大切なこと
1 タバコやお酒に気をつける
2 とんがった歯は放置しない
3 口のなかを清潔にする
4 合わない入れ歯を使い続けない
5 舌や歯ぐきが白くなったらすぐ受診する